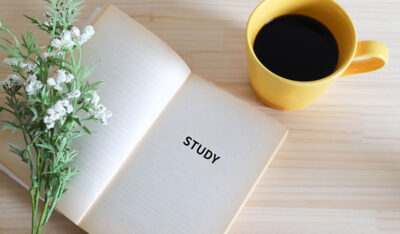中3必見!!高校受験勉強の始め方がわかる!中3のスタート講座
 公開日:
公開日:
中学3年生になると、多くの生徒が「そろそろ受験勉強を始めないと…」という気持ちになるでしょう。
しかし、いざ始めようとしても「何から手をつけたらいいのかわからない」「部活が忙しくて時間がない」「志望校もまだ決まっていない」と、不安や迷いを抱えている人も少なくありません。
受験勉強を成功させるためには、「最初の一歩」をどう踏み出すかが非常に大切です。
このコラムでは、受験勉強を効果的にスタートさせるための考え方、具体的な勉強法、そして心構えまでを、わかりやすく解説します。
今まさに始めようとしている中3生はもちろん、保護者の方にもぜひ参考にしていただければと思います。
STEP1|自分の「今」を正確に知るところから始めよう

受験勉強で最初にやるべきことは、「現状把握」です。これは、やみくもに勉強を始めるのではなく、「自分がどこまでできていて、どこが弱点なのか」を正確に理解するという意味です。
まずは、直近の定期テストや模擬試験の結果を見返してみましょう。
教科別に得点や偏差値、出題範囲、正答率、ミスの傾向などを細かくチェックし、自分の得意・不得意を洗い出します。
例えば、英語であれば「文法は得意だが、長文読解は苦手」、数学であれば「計算は早いけれど図形問題に弱い」など、できるだけ具体的に整理してみることが重要です。
この作業は面倒に感じるかもしれませんが、ここを丁寧に行うことで、今後の学習計画がブレなくなります。
また、可能であれば志望校の過去問を一度解いてみるのもおすすめです。
現時点での実力と入試レベルとのギャップが明確になり、「何をどれだけ頑張らなければならないのか」がリアルに見えてきます。
STEP2|土台を整える「基礎固め」が成功のカギ
多くの受験生がやってしまいがちな失敗の一つが、「応用問題から始めてしまうこと」です。
難しい問題を解けば成績が伸びるように思えるかもしれませんが、実はその前にやるべきことがあります。
それが「基礎の徹底」です。
中学3年生の受験勉強は、中1・中2の学習内容の復習から始めるのが正解です。
なぜなら、高校入試の問題の多くは、実は中1・中2の内容が土台になっているからです。
たとえば、数学では「正負の数」「方程式」「関数」などが複雑な図形問題の前提になります。
英語では、基本的な文法事項や単語力がないと長文読解や英作文に太刀打ちできません。
【基礎固めの方法】
- 教科書を読み直し、内容を理解しているか確認する
- 学校のワークや市販の基礎問題集を一冊完璧に仕上げる
- 理解があやふやな単元は、YouTubeやオンライン教材などで補足学習
- 解けなかった問題は「なぜ間違えたか」を分析し、ノートにまとめて復習
基礎をしっかりと積み上げたうえで、夏以降に応用問題や過去問に取り組めば、スムーズにステップアップできます。
STEP3|学習スケジュールを立てて「習慣」にする
勉強は「量」も大事ですが、それ以上に「習慣化」がポイントです。
毎日決まった時間に机に向かう習慣ができれば、受験勉強は自然と進みます。
まずは短時間からでかまいません。
【習慣化のポイント】
- 平日は1~2時間、休日は3~5時間を目安にスタート
- スマホは手の届かない場所に置く
- 「19時~21時は勉強タイム」と決めてスケジュールを固定する
- 目標を「今週は理科の電流をマスターする」など具体的に設定
初めは集中力が続かなくても、続けるうちにだんだん慣れてきます。
大事なのは「完璧主義にならないこと」。
サボってしまった日があっても、自分を責めず、翌日また軌道に戻れば大丈夫です。
STEP4|志望校の情報を調べて、目的意識を持とう
「なぜ勉強するのか」という目的意識があるかないかで、モチベーションは大きく変わります。
志望校が決まっていない人も、まずは気になる高校の情報を調べてみましょう。
【調べるべきポイント】
- 偏差値・入試科目・内申点の目安
- 学校の教育方針や特色あるコース(英語コース・探究学習など)
- 通学距離や通学手段
- 部活動の種類・実績
- 卒業生の進路(大学・専門学校・就職など)
オープンスクールに参加して、学校の雰囲気を肌で感じてみるのも良い刺激になります。
「この学校に行きたい!」という気持ちが芽生えれば、それがそのまま勉強の原動力になります。
STEP5|模試は受験勉強の“現在地”を知るための羅針盤
模擬試験(模試)は、単に学力を測るだけのものではありません。
受験勉強を進めるうえで、今の自分の実力を客観的に知り、どこを重点的に勉強すべきかを明確にする「指標」としての役割があります。
模試の結果が返ってきたとき、多くの生徒がまず気にするのは「点数」や「偏差値」かもしれません。
しかし、受験勉強において本当に重要なのは、点数そのものよりも、その結果から“どのような学習課題が浮き彫りになったか”を読み解くことです。
たとえば、数学の偏差値が高くても、よく見ると図形分野の正答率が低い。
英語の長文は得点できているが、文法問題でケアレスミスが多い。
こうした細かい分析をすることで、今後の学習における「優先順位」が見えてきます。
【模試の活用方法】
・解き直しを徹底する
模試を受けた後は、必ずすべての問題に目を通し、間違えた問題だけでなく、正解した問題も「本当に理解できていたか」を確認します。
たまたま正解していた問題も含めて、解き直しをすることで知識が定着します。
・単元ごとの得点傾向をチェックする
科目別、単元別に点数や正答率を表にして見える化すると、自分の弱点が明確になります。
特に模試の成績表には「分野別診断」や「偏差値の推移」など有用な情報が載っていることが多いので、見落とさず活用しましょう。
・目標校との距離を測る
模試では志望校の合否判定(A〜E判定)が出る場合もあります。
判定結果はあくまで目安ではありますが、自分が今どの位置にいるのかを把握し、どの科目を伸ばせば合格が近づくのかを考える材料になります。
さらに、模試を受ける最大のメリットの一つが「本番のシミュレーションができること」です。
本番の入試と同じように時間が決められ、初めて見る問題に挑むという状況は、実際の入試に近い緊張感があります。
この経験を通じて以下のような“実戦力”が鍛えられます。
- 限られた時間内で問題を取捨選択する判断力
- 試験中のメンタルコントロール(焦らない・立て直す力)
- 科目ごとの時間配分と休憩時の過ごし方
模試は受けた後が本番です。
結果をもとに「何をどう改善するか」まで考えることが、模試を受ける意味を最大限に活かすコツです。
STEP6|受験勉強は“チーム戦” 一人で抱え込まず周囲を頼ろう
高校受験という大きな挑戦に立ち向かう中で、「すべて自分の力で何とかしないと…」と孤独に戦おうとしてしまう生徒は少なくありません。
しかし、受験勉強は決して一人で戦う必要はありません。
むしろ、困ったときに相談できる人や頼れる環境を持っていることこそが、受験を乗り越える大きな支えになります。
たとえば、勉強していてわからないところが出てきたとき、自分で参考書を読んでも理解できないことがあります。そんなときに、すぐに質問できる人がいるかどうかで、学習のスピードや理解度に大きな差が生まれます。
【サポートの選択肢はさまざま】
・学校の先生に質問する
授業の内容に関する疑問や、内申対策についての相談などは、やはり学校の先生が頼れる存在です。
特に受験期は、担任の先生とのコミュニケーションが志望校選びにも影響することがあります。
・塾や家庭教師を活用する
定期的に教えてもらうことで学習のペースが保てます。
通塾型が合わない場合は、家庭教師のようにマンツーマンでサポートを受けられる環境も検討するとよいでしょう。
・オンライン家庭教師という新しい選択肢
近年では、インターネットを使ったオンライン家庭教師が注目を集めています。
画面越しでもホワイトボードや資料を共有しながら学習でき、通塾の必要がないため、時間を有効に使えるのが大きなメリットです。
オンライン家庭教師は以下のような生徒に特におすすめです。
- 部活動や習い事で時間が限られている
- 自宅で集中して学びたい
- 苦手な部分だけピンポイントで教えてほしい
- 周囲に学習塾や指導者がいない地域に住んでいる
また、保護者の立場から見ても、オンライン指導なら子どもの学習状況をそばで見守ることができ、安心感があります。
困ったときは遠慮せず、誰かを頼っていい
受験勉強において、「わからないことがあっても誰にも聞けない」「計画が立てられず、ただ時間だけが過ぎていく」——そうした悩みを一人で抱えてしまうと、だんだん勉強へのモチベーションも下がってしまいます。
「自分は頑張っているのに成績が上がらない…」と落ち込んだときこそ、第三者の視点が必要です。誰かに話すことで、自分では気づかなかった解決の糸口が見つかることもあります。
受験は確かに“個人戦”の側面もありますが、同時に“チーム戦”でもあるのです。家族、先生、指導者など、自分を支えてくれる人たちの存在を素直に頼ることで、より安心して学習を進めることができます。
まとめ
高校受験は、限られた時間の中でどれだけ効率的に準備できるかが大きなカギになります。
そしてその第一歩は、「今日始めること」。やるべきことはたくさんありますが、一つひとつ丁寧に取り組んでいけば、確実に力はついていきます。
周りと比べて焦る必要はありません。
自分のペースで、自分の道を進めば大丈夫。
今日この瞬間が、あなたの受験勉強のスタートラインです。