中学生が授業についていけない原因と解決法!親ができる効果的なサポート
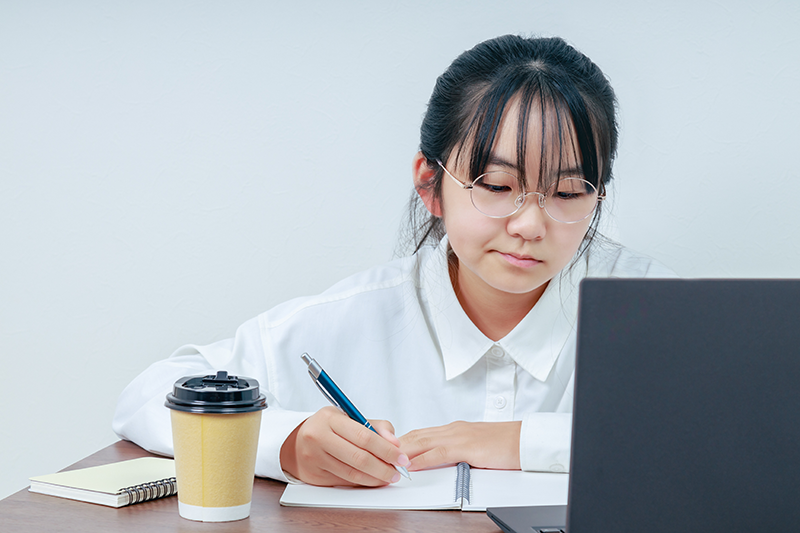 公開日:
公開日:
お子さんが中学校に進学してから、「授業の内容が難しい」「テストの点が下がった」「前よりも勉強に自信をなくしている」と感じたことはありませんか?
小学校と比べて中学校の学習は一気に難易度が上がり、部活動や友人関係など新しい環境も加わるため、授業についていけなくなる生徒は決して珍しくありません。
しかし、この時期に適切なサポートを行えば、学力の遅れを取り戻すだけでなく、勉強への前向きな姿勢を育むきっかけにもなります。
中学校の学習が難しく感じられるのはなぜか
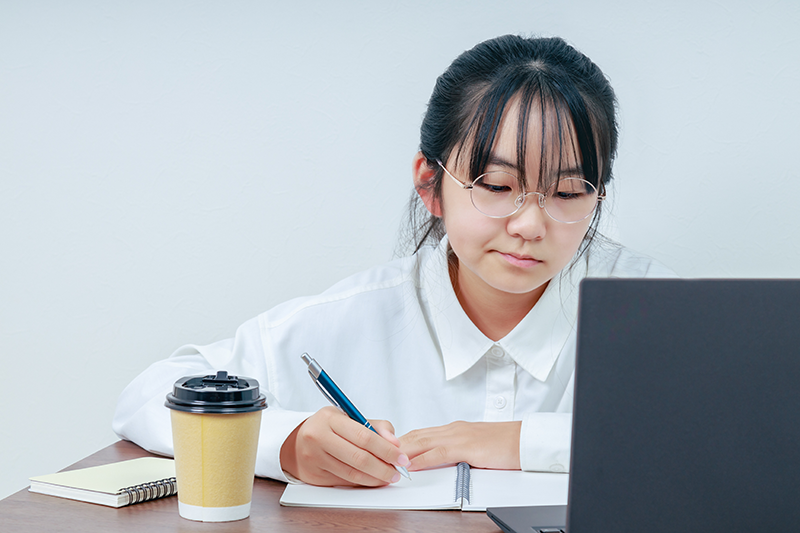
学習内容のレベルアップ
小学校から中学校に進学すると、学習の内容と量は大きく変化します。
小学校では基礎的な計算や読み書きを中心に学んでいたのに対し、中学校では「知識の理解」にとどまらず「論理的に考える力」「自分の考えを説明する力」が必要になります。
数学を例に挙げると、分数や小数の計算といった基礎的な内容から、一気に「一次方程式」「比例・反比例」「関数」「図形の証明」などへと進みます。
答えを出すこと自体はもちろん重要ですが、それ以上に「なぜその答えにたどり着けるのか」を説明する力が求められます。
これまで「なんとなく計算できた」という感覚で学んできた子どもにとっては大きなハードルになりやすいのです。
英語も大きな変化の一つです。小学校ではアルファベットの読み書きや簡単な会話表現が中心でしたが、中学校では文法の理解、長文読解、英作文、リスニングなど多面的な力が必要になります。
覚えるべき単語数も一気に増えるため、暗記が苦手な子どもにとって「勉強がつらい」と感じやすい単元になりがちです。
理科や社会も単なる暗記にとどまりません。
理科では実験結果から法則を導いたり、グラフや表を読み取る力が求められます。
社会科では、地理で地図や統計資料を活用する力、歴史で出来事を関連づけて時系列に整理する力が必要になります。
単語や用語を覚えるだけではなく、背景や関連性を理解しなければ学習が進みにくくなるのです。
小学校の基礎が不十分な状態で進学すると、新しい単元でつまずいたときに「なぜわからないのか」が本人にも把握できず、勉強そのものに苦手意識を持ってしまうこともあります。
この「わからない状態を放置すること」が、授業についていけなくなる大きな要因です。
学習習慣の差が成績に直結する
中学校の授業は小学校以上に進むスピードが速く、授業を一度聞いただけでは理解しきれない場面も多くなります。
ここで大きな差を生むのが「家庭学習の習慣」です。
毎日少しずつ復習する生徒は学んだ知識が定着しやすく、次の授業でも余裕をもって取り組むことができます。
例えば「その日の授業で習った英単語をその日のうちに5回書いて覚える」「数学の例題をもう一度解き直す」といった小さな積み重ねが大きな差になります。
一方で、家庭学習の習慣が身についていない生徒は「授業中に理解できなかった部分」をそのまま放置してしまい、時間が経つにつれて知識の穴が広がっていきます。
気づいたときには復習すべき範囲が膨大になり、「何から手をつければいいのか分からない」という悪循環に陥りがちです。
さらに、部活動や習い事も成績に影響を与えます。
中学校生活では部活に多くの時間と体力を使うため、帰宅後は疲れて勉強を後回しにしがちです。
「宿題は後でやる」と思いながら寝てしまい、翌朝慌てて提出物だけを済ませるという生活が続くと、授業の理解度はどんどん下がってしまいます。
日々の生活の中で、学習時間をどのように確保するかが大きなポイントとなるのです。
心理的な要因や生活環境の影響
中学生は心身の成長が著しい時期であり、学習以外の要因が成績に影響することも少なくありません。
思春期特有の悩み
友人関係のトラブルや進路への不安から、気持ちが不安定になり集中力が落ちることがあります。
特に人間関係の悩みは勉強への意欲を一気に削ぐ大きな要因になりやすいです。
生活習慣の乱れ
スマートフォンやゲームの長時間利用、睡眠不足、朝食を抜くといった生活習慣の乱れは、脳の働きを低下させます。
十分な休養や栄養が取れていないと、授業を受けても内容が頭に入らない状態になってしまいます。
自信の低下
一度つまずくと「自分は勉強ができない」と思い込んでしまい、挑戦する意欲を失いやすいのも中学生の特徴です。
特にテストでの失敗や周囲との比較によって自信をなくし、そのまま学習意欲を失ってしまうケースは珍しくありません。
これらの要因が重なると、「授業についていけない」という感覚を強めるだけでなく、学習そのものを避けるようになってしまうのです。
親御さんができる具体的なサポート
学習状況を丁寧に把握する
子どもが「どの教科」「どの単元」でつまずいているのかを知ることが第一歩です。
テスト結果だけではなく、普段のノートの取り方や宿題の解き方、学校からの連絡や本人の言葉からもヒントを得られます。
大切なのは責めるのではなく、課題を一緒に探して解決しようとする姿勢です。
「ここまではできているね」「次はここを一緒にやろう」と声をかけることで、安心感とやる気を引き出せます。
家庭学習のリズムを一緒に作る
最初から長時間の勉強を求めると反発を招きやすいので、短時間の集中から始めることが効果的です。
「夕食前に20分だけ英語」「寝る前に数学の問題を1問」など、小さな習慣を毎日続けることで勉強が生活の一部となります。
親が「やりなさい」と言うより、「一緒にやろう」と寄り添う姿勢を見せることで、子どもも前向きに取り組みやすくなります。
小さな成功体験を積ませる
難しい問題ばかりに取り組ませると、自信を失うリスクがあります。
大切なのは「できた!」という感覚を積み重ねることです。
例えば「昨日より計算スピードが上がった」「単語テストで前よりも点数が取れた」など、小さな達成を褒めることが、次への意欲を生みます。
これがやがて「もっと頑張ろう」という学習姿勢につながります。
感情面の支えを忘れない
保護者の言葉は子どもの心に強く影響します。
「どうしてできないの?」と叱るのではなく、「ここまで頑張ったね」「一緒に工夫しよう」と肯定的な言葉をかけることで、子どもは安心して勉強に向き合えるようになります。
勉強そのものだけでなく、努力や気持ちを認めることが、学習意欲を継続させる大きな支えになります。
まとめ
中学生が授業についていけなくなる背景には、学習内容の難化、学習習慣の不足、そして心理的・生活的な要因があります。
しかし、親御さんが子どもの現状を理解し、家庭学習の習慣づけや小さな成功体験の積み重ねを支援し、さらに気持ちを受け止める姿勢を持つことで、子どもは再び学習に自信を取り戻せます。
授業についていけないと感じたときこそ、親のサポートが最も大切なタイミングです。
焦らず、長い目で見て支え続けることが、子どもの成長につながるのです。





