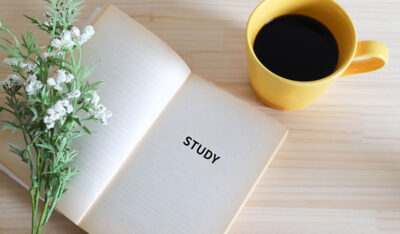中学生が家庭で勉強しないのはなぜ?5つの原因と親ができるサポート法
 公開日:
公開日:
「家では全く勉強しない」「宿題も手をつけずにスマホばかり」そんな姿に悩む保護者の方は少なくありません。
中学生になると学習内容が高度になり、学校の成績や進路が現実味を帯びてくるため、家庭学習の必要性が高まります。
しかし現実には、多くの子どもたちが家庭での学習に消極的な様子を見せています。
では、なぜ中学生は家庭学習に取り組めないのでしょうか。
単なる怠けや意志の弱さと片づけるのではなく、その背景にある要因を探ることで、改善の糸口が見えてきます。
本記事では、中学生が家庭学習を避ける主な理由と、保護者ができる具体的なサポート方法、そして実践的な解決策をご紹介します。
中学生が家庭学習をしない・できない理由とは

勉強の必要性を感じていない
中学生の中には、「なぜ勉強しなければならないのか」がピンときていない子もいます。
勉強の目的がテストの点や成績といった短期的なゴールにとどまっていると、やる気が持続しにくくなります。
保護者ができるサポート
お子さまの興味関心に合わせて、「好きなこと」と勉強を関連づけてあげましょう。
たとえば「ゲームを作るには英語や数学が大事なんだよ」といった声がけで、勉強の意味が身近に感じられるようになります。
解決策
- 将来の夢や目標を一緒に考える時間を設ける
- 興味のある分野に関連する職業や進路を調べてみる
- 学んだことがどんなふうに社会とつながるか、動画や体験談を一緒に見る
学校の授業についていけていない
授業で理解が不十分だと、家で復習するのも困難になります。
「分からないからやりたくない」と避けてしまい、さらに遅れが広がるという悪循環に陥ることもあります。
保護者ができるサポート
日常の会話で授業の様子を自然に聞き出しましょう。
「今日の理科、面白かった?」といった質問が会話のきっかけになります。
解決策
- 苦手な単元を一緒に確認し、ポイントを整理してあげる
- 学校以外の学習サポート(家庭教師・オンライン指導・学習塾)を検討
- 解けるレベルまで戻って“わかる喜び”を実感させる
勉強に適した環境が整っていない
スマートフォンやテレビ、ゲームの誘惑がある環境では、集中力を保つのは難しいものです。
また、家族の生活音や照明など、意外な点が勉強の妨げになっている場合もあります。
保護者ができるサポート
勉強時間中はできるだけ家族全体で静かな時間をつくり、スマホやテレビの使用ルールも共有するのが効果的です。
解決策
- 自室ではなくリビング学習に切り替える
- スマホやゲーム機を「時間制」にして、使える時間帯を決める
- 文具や教科書を一か所にまとめた「学習セット」を準備し、すぐに勉強に取りかかれるようにする
自己管理能力がまだ未熟
中学生はまだ、自分で計画を立てて実行する力が発展途上です。
「やらなきゃ」と思っていても、時間管理がうまくいかず、後回しになってしまうことも多々あります。
保護者ができるサポート
「今日の夜は何を勉強する?」など、一緒にスケジュールを立てることから始めてみましょう。
細かすぎず、ざっくりとした計画でも効果があります。
解決策
- タイマー学習(25分集中+5分休憩など)を取り入れる
- 1日1つの小目標(例:漢字10個だけ覚える)に挑戦させる
- 親子で「できたことを見える化」するチェックリストを使う
心の不調やストレスを抱えている
人間関係のトラブル、将来への不安、学校での失敗体験など、心に重荷を抱えているとき、勉強する余裕などありません。
「怠け」ではなく「疲れ」や「落ち込み」が原因の場合もあるのです。
保護者ができるサポート
「ちゃんと話を聞く」ことが何より大切です。
勉強の話題ばかりでなく、日常のちょっとした出来事を話せる関係づくりを心がけましょう。
解決策
- 勉強以外の楽しみ(趣味、散歩、好きなテレビ番組)で気分転換を促す
- 話しかけるタイミングや声のトーンに気を配り、プレッシャーを与えない
- 必要に応じて学校の先生や外部の専門家に相談する選択肢も視野に入れる
家庭学習を習慣化するためのちょっとした工夫
家庭学習において、いきなり「毎日1時間勉強しよう!」と高い目標を立てるのは逆効果になることもあります。
最初から完璧を求めすぎると、継続できなかったときに自己否定につながってしまい、やる気を失ってしまうリスクがあります。
重要なのは、少しずつでも毎日机に向かう“流れ”を作ることです。
たとえ10分程度の学習でも、「今日もできた」という達成感が、自信や継続につながっていきます。
ここでは、家庭学習を習慣として定着させるための、小さなけれど効果的な工夫をご紹介します。
学習前に5分間だけ机の上を片付ける
「さあ、勉強しよう」と思っても、机の上にプリントや本、文房具、お菓子の袋などが散らかっていると、気が散ってしまい、集中する前にやる気がなくなってしまうこともあります。
そのため、学習を始める前に“環境を整える行動”をルーティン化することが有効です。
とくにおすすめなのが「5分間だけ机の上を片付ける」こと。
この時間はただ掃除をするのが目的ではなく、頭と気持ちを切り替える“スイッチ”としての役割を果たします。
この習慣がつくと、机を片付けること自体が「これから勉強するモードに入る合図」になり、自然と学習への集中力が高まっていきます。
学習が終わったら“ごほうびタイム”をつくる
「やったら終わり」ではなく、「やった後にちょっとした楽しみが待っている」という構造をつくると、学習へのモチベーションがぐっと上がります。
たとえば、以下のような“ごほうび”が挙げられます。
- 好きなおやつやデザートを用意する
- 学習後に10分だけ動画やゲームの時間をとる
- シールやスタンプを集めて、一定数で好きなプレゼントと交換
このようなごほうびは、短期的な達成感と楽しさを実感させ、次回へのやる気を引き出す原動力になります。
ポイントは、勉強の量ではなく「やった」という事実に対して報いることです。
たとえ5分の取り組みでも、“行動できたこと”自体をしっかり評価してあげましょう。
家族も一緒に静かな時間を過ごす
子どもだけに「勉強しなさい」と言っても、周囲がにぎやかにテレビを見ていたり、お菓子を食べていたりすれば、「なんで自分だけ?」と反発心が芽生えてしまいます。
そういった気持ちを軽減するには、家族も一緒に“静かな時間”を共有するのが効果的です。子どもが勉強している間、親も読書やパソコン作業、手帳の整理などをして過ごすことで、「勉強は特別なことではなく、家庭内の当たり前の流れ」と感じてもらいやすくなります。
また、こうした静かな時間が、親子の自然な会話のきっかけになることもあります。
学習時間を“孤独な戦い”にせず、「みんなも頑張っている」という一体感を演出していくことが、家庭学習の習慣化につながります。
習慣化の第一歩は「小さな成功体験」から
最初は10分だけでもかまいません。
重要なのは、毎日「少しでもやった自分を認める」こと。たとえば、1週間続いたらシールを貼って見える場所に飾る、親がその努力に言葉でしっかり反応するなど、“続けている自分”を見える化する仕組みを取り入れると、自己肯定感にもつながります。
やる気が自然と湧いてくる状態を作るには、「成功体験→自信→継続」という流れを少しずつ積み重ねていくことが何よりの近道です。
オンライン家庭教師を活用するという選択肢
どうしても家庭では学習のリズムが整わないとき、外部のサポートを活用するのも効果的です。
特に最近では、通塾せずに自宅で指導を受けられるオンライン家庭教師が注目されています。
オンライン家庭教師のメリット
- 子どもの性格や学力に合わせて指導内容を柔軟に変えられる
- 移動がなく、リラックスした自宅環境で学べる
- 1対1なので、質問しやすく苦手分野に集中できる
さらに、保護者の方が指導の様子をそばで見られることも安心材料の一つです。
多くのサービスでは無料体験授業が用意されているため、まずは体験してお子さまとの相性を確かめてみるのがおすすめです。
家庭内だけでの解決が難しい場合は、無理をせずプロの力を借りることも前向きな選択です。
まとめ
中学生が家庭学習をしない理由には、「やる気がない」と一言で片づけられない深い背景があることがわかります。保護者として大切なのは、原因を見つけて寄り添いながら、少しずつでも前進する手助けをすることです。
「家で勉強する習慣」は、完璧を目指すより、「昨日より1歩前進する」ことが大切です。
焦らず、あたたかく見守りながら、無理なく取り組める環境ときっかけをつくっていきましょう。