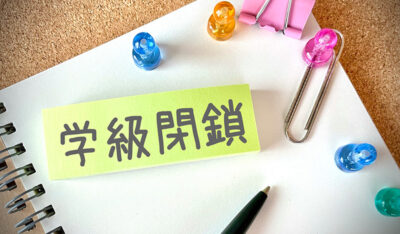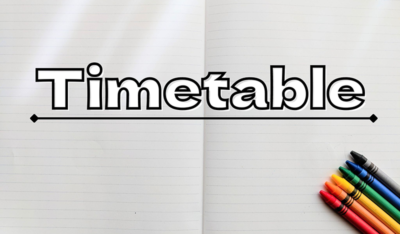算数が得意になる家庭での工夫!子どもの苦手意識を解消するために親ができること
 公開日:
公開日:
「算数が嫌い」「計算が苦手」と子どもが言い出すと、保護者としては将来の勉強や進学にまで不安を感じてしまうものです。
算数は小学校から高校までずっと続く基盤科目であり、つまずきを放置すると学年が上がるにつれて理解が追いつかなくなることも少なくありません。
しかし、逆に言えば 家庭でのちょっとした関わり方や学習環境の工夫によって、算数に対する苦手意識は大きく改善できます。
ここでは、保護者が日常生活の中でできる実践的なサポート方法を詳しくご紹介します。
「小さな成功体験」を積み重ねることが第一歩

算数が苦手な子どもは、「やってもできない」という思い込みにとらわれがちです。
これは失敗体験が繰り返されてきた結果であり、その悪循環を断ち切るには 「小さな成功の積み重ね」 が欠かせません。
例えば、あえて学年より一段階やさしい問題から始め、「できた!」という感覚を味わわせると、子どもの表情は一気に変わります。
100点を取らせる必要はなく、たとえ5問中3問解けたとしても「半分できたね!次は4問に挑戦してみよう」と前向きに評価することが大切です。
計算カードを使って「1分間で何問できるか」競うゲームにすると、勉強が遊びに変わりやすくなります。
こうして日常的に小さな達成感を積み重ねることで、子どもは「自分もやればできる」という自己効力感を少しずつ取り戻していきます。
日常生活の中に算数を取り入れる工夫
算数は学校で教科書を使って学ぶだけのものではなく、私たちが暮らす日常のあらゆる場面に結びついています。
机に向かっての学習が苦手な子どもでも、日常生活の中で自然に算数を体験できれば「学ぶことの意味」を実感しやすくなり、知識が身につきやすくなります。
親が少し意識して問いかけを工夫するだけで、日常が算数学習の教材に早変わりします。
買い物での工夫
スーパーやコンビニでの買い物は、子どもにとって算数の実践の場です。
「100円のお菓子を3つ買うといくら?」
「500円持っていたらおつりはいくら?」
「1個120円のリンゴを4つ買うと合計でいくら?」
といった計算は、ただの数字ではなく実際のお金や商品と結びついているため、理解が深まりやすくなります。
実際にレジで支払わせると「自分が計算した通りの金額が出てきた!」という体験になり、算数の価値を肌で感じることができます。
さらに高学年になれば「10%引きだといくら安くなる?」といった割引計算に挑戦させると、実生活に直結した算数の力が育ちます。
料理での工夫
料理は算数の宝庫です。
レシピを見ながら材料を計量する場面では、分数・小数・割合といった単元を自然に学ぶことができます。
「卵を6個使うレシピを半分にすると何個必要?」
「水200mlの2倍は何ml?」
「砂糖大さじ3を2人分にするなら、4人分ではいくつ必要?」
このような計算を実際にやってみると、分数や比率が「ただの記号」から「料理を成功させるための道具」へと意識が変わります。
料理を通して学ぶ算数は、子どもに「算数は生活に直結して役に立つもの」という気づきを与え、自発的な学びにつながります。
移動の場面での工夫
登下校や家族での外出も、算数を取り入れるチャンスです。
「学校まで徒歩15分だから往復で何分?」
「家から駅までの距離が2km。分速80mで歩いたら何分かかる?」
「地図を見てA地点からB地点までの距離はどれくらい?」
時間や距離を算数に結びつけることで、単なる数字が「現実世界を理解するためのツール」として機能します。
さらにバスや電車の時刻表を使い「乗り換え時間を含めると何分かかる?」と考えさせると、算数の応用力や論理的思考の訓練にもなります。
家庭での工夫を日常化する
買い物・料理・移動のほかにも、家庭の中には算数を取り入れられる機会がたくさんあります。
おこづかいの管理を通して「予算」「収支」「貯金」を学ぶ
トランプやサイコロの遊びを通して数の組み合わせや確率を体験する
家の電気料金の明細を見ながら「1kWhあたりいくら?」と考える
こうした日常の工夫を積み重ねることで、子どもは「算数=難しい勉強」ではなく「算数=生活に役立つスキル」というポジティブな意識を持つようになります。
ポジティブな声かけで意欲を育てる
子どもにとって、親の声かけは何よりも大きな励みです。
「どうしてこんなこともできないの?」という言葉は、努力する気持ちを一瞬で消してしまいます。
代わりに、次のような前向きな言葉を意識してみてください。
「ここまでは自分で考えられたね」
「あともう少しで正解に届くよ」
「間違えたけど考え方は合ってるから惜しい!」
このような言葉は、子どもに「失敗してもいい」という安心感を与えます。
特に算数に苦手意識がある子どもにとって、安心して挑戦できる環境こそが一番の成長の土台です。
視覚的な教材や遊びを取り入れる
数字や記号だけを見て理解するのが難しい子には、 視覚的・体験的な教材 を活用すると効果的です。
ブロックや積み木で足し算・引き算を実演する
おはじきやカードを並べて数の操作を体験する
算数パズルやアプリで遊びながら論理的思考を養う
低学年の子ほど、具体物を操作する体験を通して理解が深まります。学習が「遊び」に近づくことで、算数へのハードルが下がり、自然に「もっとやりたい」という気持ちが生まれやすくなります。
苦手単元を早めに見極める
算数は積み上げ型の教科であるため、ある単元でつまずくと、その後の学習にも連鎖的に影響します。
例えば、九九が不十分なまま分数の計算に進むと「約分」「通分」が理解できず、文章題になるとさらに混乱します。
保護者は子どもの様子を観察し、
どの問題で時間がかかっているか
どの単元になると嫌がるか
を見極めましょう。
苦手が明確になれば、その単元を重点的に復習する、映像授業を併用する、参考書を使って繰り返すといった対策がとれます。
「苦手の早期発見と集中的な補強」が、算数嫌いを長引かせない最大のポイントです。
学習環境を整えて集中力を高める
学習の成果は勉強方法だけでなく、 学習環境 に大きく左右されます。
テレビやスマホが気にならない静かな場所を確保する
机の上は必要な教材以外を置かず、整理整頓する
長時間だらだら勉強するより、20〜30分の短時間集中を繰り返す
こうした工夫は集中力を高めるだけでなく、「勉強モードに切り替える」習慣を作ります。
環境を整えることは算数嫌いを克服するための、意外に大きな第一歩です。
学校外のサポートも上手に活用する
どうしても家庭だけでは限界を感じる場合、外部のサポートを取り入れるのも有効です。
塾や通信教材はもちろん、近年は オンライン家庭教師 も人気です。
オンラインなら自宅から受講でき、移動時間が不要なため習い事や部活と両立しやすいという利点があります。
また、苦手単元をピンポイントで指導してもらえるので、短期間で「わかった!」という実感を得やすいのも魅力です。
家庭と学校以外の第三者のサポートが加わることで、子どもは「自分には味方がいる」と感じ、算数への抵抗感を和らげやすくなります。
まとめ
算数を得意にするために必要なのは「才能」ではなく、小さな自信の積み重ねと家庭でのサポート です。
生活の中で算数に触れる工夫、ポジティブな声かけ、そして学習環境の整備を意識することで、子どもは少しずつ算数に対する抵抗感をなくしていきます。
そしてもし家庭だけでのサポートに限界を感じたら、外部のサポートを取り入れるのも有効な選択です。
大切なのは「算数はやればできる」という成功体験を子どもに積ませてあげること。
これが、算数嫌いを克服し、学びを楽しめるようになる一番の近道です。