内申点アップを狙う!中学生に必要な定期テスト前の家庭学習法
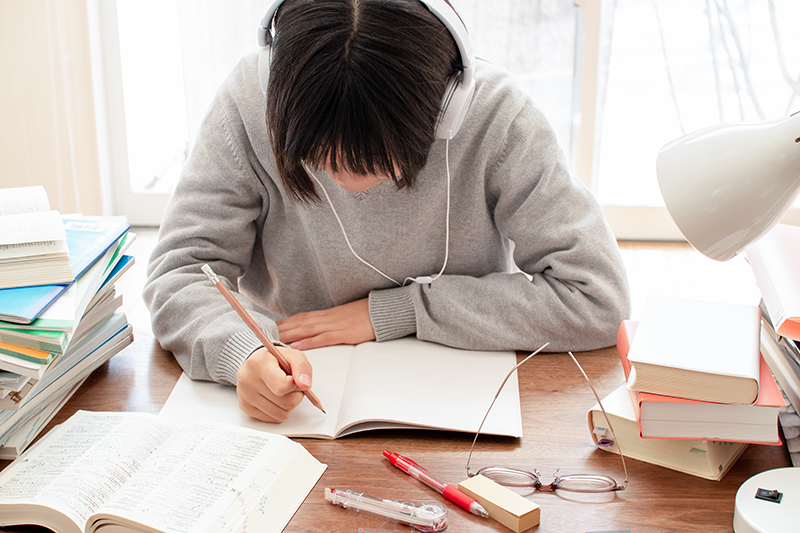 公開日:
公開日:
中学校生活において、避けて通れないのが「定期テスト」です。
年に数回行われるこのテストは、単なる学力のチェックではなく、通知表の評価、そして最終的には高校受験に直結する重要な指標です。
とくに公立高校入試では、内申点が合否を左右することも少なくありません。
そのため、定期テストにどう向き合うかは、中学生にとって非常に大きなテーマです。
では、定期テストでしっかりと成果を出すために、家庭ではどのような学習を心がけるべきなのでしょうか?
本記事では、「なぜ定期テスト対策が大切なのか」「家庭学習はどう進めるべきか」「効果的な学習スタイルは何か」について、詳しく解説していきます。
定期テストの重要性とは?
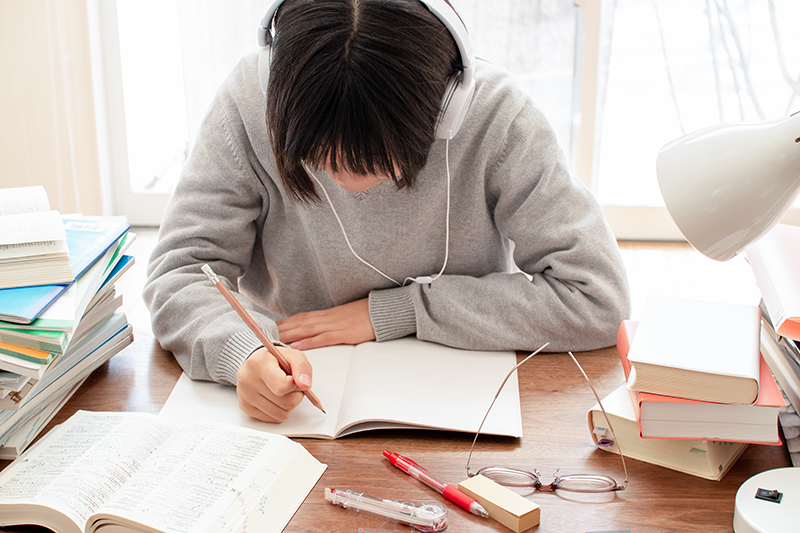
定期テストの結果は、すぐに目に見える形で自分の学力が表れます。
点数や順位という具体的な数値になることで、自分の得意・不得意も把握しやすくなります。
しかし、それだけではありません。
中学校では成績=通知表の評価が「内申点」として蓄積されます。
特に中学1年生から3年生までの全体的な成績が、高校受験時に提出される内申点として活用されるため、1回1回のテストが将来の進路に直結することになるのです。
例えば、主要5教科(英語・数学・国語・理科・社会)だけでなく、副教科(音楽・美術・技術・保健体育など)も同じように内申に影響します。
副教科のテストでも油断できないのはこのためです。
早いうちから“テスト勉強の型”をつくることがカギ
中学1年のうちに、自分なりのテスト勉強のスタイルを確立することができれば、学年が上がるにつれて難しくなる内容にも、柔軟に対応できるようになります。
「いつから勉強を始めるか」「どの教科にどのくらい時間をかけるか」「復習はどんな方法でするか」など、自分なりのルールを確立することはとても大切です。
テスト勉強といっても、ただ教科書を読んでノートを見返すだけでは不十分です。
- 重要語句を自分の言葉で書き出す
- 学校で配られたワークを繰り返し解く
- 一度間違えた問題は印をつけて再度解き直す
- 教科書に書かれている図や資料を丁寧に読み解く
このような「アウトプット型」の学習が、点数につながる力になります。
直前の詰め込みに頼らない、日常の積み重ねが大切
テスト1週間前から一気に詰め込むスタイルの勉強は、一見効率的に思えるかもしれません。
しかし実際には、知識が一時的に頭に入るだけで、テスト後にはすぐに忘れてしまうケースが多く見られます。
また、詰め込み勉強には大きなストレスがかかり、「勉強=しんどいもの」というイメージが定着してしまうこともあります。
これがやる気の低下や学習離れを招く原因になることも少なくありません。
だからこそ、定期テストで安定した結果を出すには、「日常的な家庭学習」の積み重ねが欠かせません。
1日15分でもいいので、毎日決まった時間に勉強する習慣をつけておくことで、テスト前に焦ることなく自然に準備が整うようになります。
家庭学習の効果を高める具体的な方法
定期テストに向けて家庭で学習する時間をどう活かすかによって、テスト結果は大きく変わってきます。
塾や学校の授業だけでなく、自宅での学びがしっかりしていれば、理解度が深まり、自信を持ってテストに臨めるようになります。
ここでは、テスト対策として効果を上げるための家庭学習のポイントを、より具体的に紹介していきます。
学習計画を立てる:目標から逆算して“やるべきこと”を見える化しよう
ただやみくもに勉強を始めても、時間ばかりが過ぎてしまい、効率的とは言えません。
そこでまず大切なのが、「学習計画を立てること」です。
理想はテスト日の2〜3週間前から逆算して、教科ごとの優先順位を決め、1日の学習内容を具体的にリストアップすることです。
例えば、テスト3週間前の週は「全体の把握と苦手単元のあぶり出し」、2週間前は「問題演習と理解の強化」、1週間前は「総復習と暗記の徹底」といったように、週単位でテーマを分けると、迷わず勉強に取りかかれます。
さらに、1日の中で何をどれだけやるのかを「ToDoリスト」に書き出すことで、自分がやるべきことが明確になり、達成感も得やすくなります。
学校ワークを徹底的に活用:テスト範囲の“答え”はここにある
学校で配られるワークやプリントは、テストに直結する非常に重要な教材です。
多くの先生は授業で扱った内容をテストに出題するため、学校ワークをしっかりこなしておくだけでも点数に直結します。
まずはワークを1周やってみて、わからなかった問題に印をつけておきましょう。
2周目では、その印のついた問題だけを重点的に復習します。
3周目は時間を測ってテスト形式で解いてみると、本番を意識した練習になります。
特に英語や数学などは、「解き方のパターンを覚える」ことが重要なので、同じ問題を繰り返すことで解法が身につきます。
また、理科や社会では、「用語や語句の暗記」だけでなく、「流れや因果関係の理解」も必要です。
ワークの解説部分までしっかり読み込むことが、得点力アップにつながります。
苦手な単元を見逃さない:苦手は“発見”できれば半分解決したようなもの
多くの生徒がつまずくポイントが、「苦手な単元の放置」です。
難しい問題や、わかりにくい単元はつい後回しにしがちですが、それを放置してしまうと、学年が上がったときにさらに理解できなくなり、学力の伸びを妨げる原因となります。
苦手を克服するには、まず“どこが苦手なのか”をはっきりさせることが大切です。
過去の小テストや提出物を見返して、自分がミスした問題をチェックするのも有効です。
苦手単元を見つけたら、それだけを集中的に勉強する「克服日」をつくってみましょう。
例えば「土曜日の午前中は数学の関数だけに集中する」など、テーマを絞って勉強することで、効率よく弱点を補強できます。
また、わからないままになっている部分は、オンライン家庭教師などを活用して、その場で質問し、確実に理解していくこともおすすめです。
アウトプットを意識する:記憶は“使ってこそ”定着する
「見るだけ」「読んだだけ」では、なかなか記憶に残りません。定期テスト対策で大きな差を生むのは、“アウトプット”の量と質です。
つまり、「覚えたことを使う」ことで、知識が脳に定着していきます。
具体的には以下のようなアウトプット方法があります。
- ノートに書きながら暗記する
- 教科書や資料集を見ずに、思い出しながら図や表を再現する
- 自分の言葉で、友達や家族に内容を説明してみる
- 英単語を見て意味を書く、逆に日本語から英単語を書くテストを自作する
- 理科や社会は、覚えた内容を紙にまとめる「マイ教科書」を作ってみる
また、「一度解いた問題を数日後にもう一度解く」という“間隔をあけた復習”も非常に効果的です。
記憶は時間とともに薄れていくものですが、タイミングを見て再び使うことで、記憶が長期的に残りやすくなります。
集中力が続かないときの対策
家庭での学習がうまく進まない一番の理由は、「集中力が続かない」ことです。
スマホやゲーム、テレビなどの誘惑が多い家庭環境では、集中できる時間が限られてしまいます。
そんなときは、以下のような工夫を取り入れてみましょう。
- スマホは別の部屋に置く
- 勉強時間を25分、5分休憩の「ポモドーロ・テクニック」で区切る
- 「まずは5分だけやってみる」という小さな一歩から始める
また、「家ではどうしても集中できない」という場合には、オンライン家庭教師のように、画面越しに誰かと一緒に学ぶスタイルもおすすめです。
質問しやすく、定着度の高い学習が可能になります。
まとめ
定期テストで結果を出すためには、早い段階で自分に合った学習方法を確立し、日々コツコツと積み重ねていくことが何より大切です。
学年が進むにつれてテストの難易度は上がっていきますが、基本となる勉強習慣が身についていれば、無理なく乗り越えられるようになります。





